琴の名人、鯉に乗って無双をする――琴高仙人

琴高 (きん-こう)
趙の時代の仙人
・能力・
涓彭の術という寿命に関する術が使えた。
琴の名人で、多くの人から愛された。
鯉を従えて悪い龍を退治した。

今日は琴高仙人という仙人についてだ。

琴ということは琴を弾くんですか?

鋭いね。琴の名人としても知られた。そういう所から多くの画家たちに愛されたのだが……それは後で話すよ。

琴高仙人は、趙の国の出身で、長らく諸国を放浪していたという。話の時代は宋の末期……大体紀元前300年頃かな。
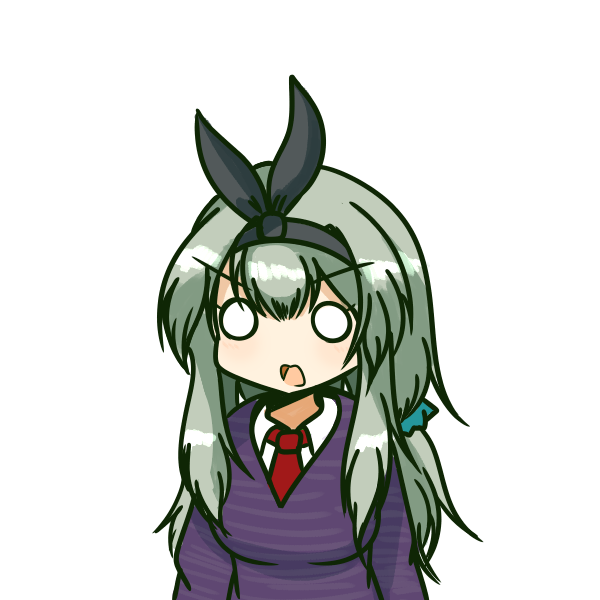
紀元前!? 数千年のスケールですね……!

しかも宋の時代に生きていた頃には既に200歳を超えていたというのだから、実際はもっと古いのかもしれない……話の舞台では、宋の康王に仕えていたという事になっている。この康王という人は、中国王朝史上でも稀を見る暴君として語られるのだが、琴高の逸話ではそんな感じの風はない。もっとも、康王の評価というのはどこまで本当なのか判らない所があるんだが……。

その康王の舎人としていたんだね。琴高は。

舎人(とねり)?

使用人というか、なんというか……まあ権力者の下で雑務とか雑用を行う存在というべきかな。ピンからキリまであるけど。その時には既に200年以上生きていたという。
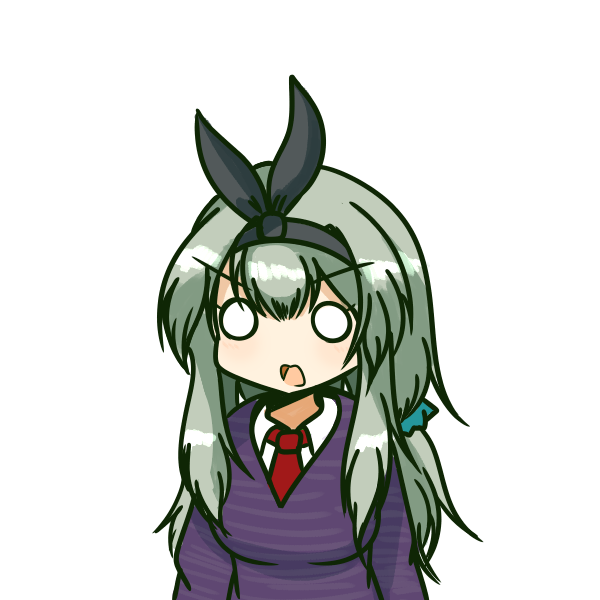
200年?!

涓彭(けんほう)の術というものが使えたそうな。ハッキリとしたことは説明為されてないが、寿命や見た目に関する術だろう。術の頭に着けられているのは、涓子・彭祖という伝説上の仙人・思想家で、特に彭祖は800年近く生きた人物として知られていた。そんな二人の名前を付けるのだから、仙人系の秘術と見るのが妥当な所であろうね。

なるほど……それはすごいですねえ……

ある時、涿州という所で、弟子たちにこう宣言したそうな。「涿水にいる龍子を捕らえてくる」と。涿州というのは、後の河北省にあった土地の一つ。涿州にあった川に入ると訳するのがいいかな。

龍の子を……? それまたどうしてですか……?

これも説明がなされてないが、困らせる龍のたぐいだったんだろうね。龍は神聖なイメージを持つ一方で、雷や大雨をもたらすバケモノ的なイメージも持っていた。龍の子でもそういう力があれば脅威といえるだろう。その退治に行く――と解釈すべきだろうね。

弟子たちに「龍子を捕らえる」と宣言した後、「何日に帰る」と約束までしてきた。弟子たちは「その日まで私たちは潔斎をして、川のほとりに祭壇をもうけて先生の帰還を待っております」と答えた。潔斎というのは身をキレイにする事……一「身をきれいにして祭祀や祈念していた」という事かな。

昔のことですから、お祭りや祭祀が重要視されたでしょうねえ……

文中では説明がないが、多分琴高は水の中に飛び込んだのだろう。噂が噂を呼んで、川のほとりには人々が押し掛けたという。気持ちはわかるね、「本物の仙人なのだろうか」という疑問や「奇跡をみたい」という心や、或いは冷やかし半分とかもあるだろう。人は増え続け、約束の日には数万の人が集ったという。
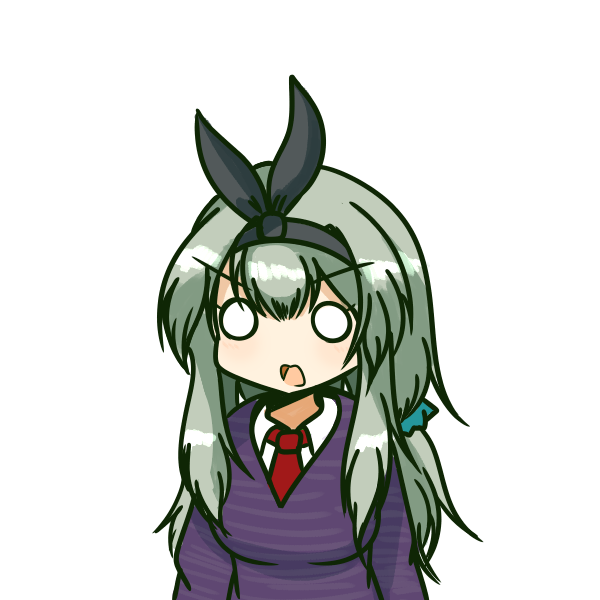
数万ってちょっとした町がつくれるレベルじゃないですか!

それくらい期待や興味を持つ人が多かったんだろう。約束の日、人々が様々な感情や声を上げる中、水面に人影が現れた。すると大きな鯉に乗った琴高が現れたという。琴高のコメントが出ていないのが残念だが、さっそうと現れた所を見ると約束通り龍を退治したのだろう。

それで鯉に乗った仙人という事なんですね?

そういう事。そして、琴高はその地に一月ほどのとどまっていたかと思うと、鯉たちを引き連れて、また川に入って去ってしまった――という。そして、その後の消息は分からない。
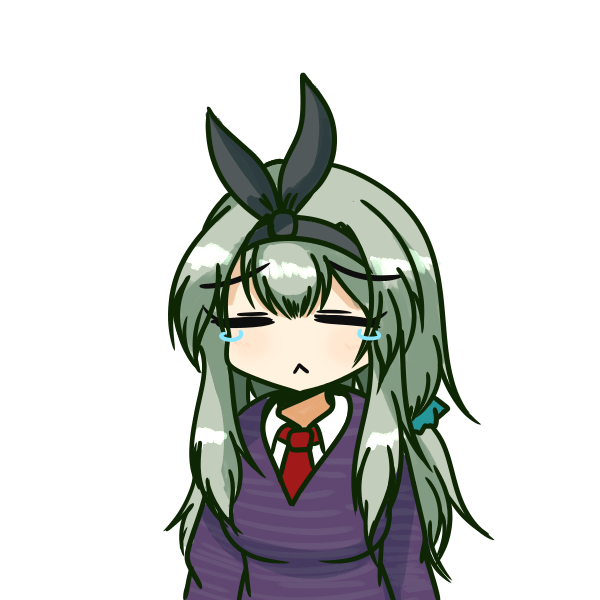
ええ……鯉に乗ってそのまま消えてしまった……。しかも続きがないなんて、尻切れトンボみたいですね……。

すごい術を使う人の事だから、その後も生き続けたと思うが、それは想像の範囲を抜け出さないだろうね。何はともあれ、琴高の話はこれで終わり。しかし、この逸話は、多くの画家や作家に愛されて、書かれるようになった。

へえ、画家たちにですか?

中国ではそれこそ千何百年と様々な画題で書かれた。鯉に乗って人々を助けるという姿が、水墨画なんかとウマが合ったんだろうね。そして信仰的な意味においても。

日本では、室町時代に水墨画が持ち込まれて以来、関係者がこぞって書き始めた。当初は現地の真似だったのかもしれないが、その内、画風を確立して、名画と呼ばれるものを残した。有名無名問わず、多数の作品があるというが、有名な書き手だと、雪村周継、尾形光琳、酒井抱一、加納探幽、円山応挙、狩野芳崖なんかがあるという。

一流の書き手ばかりですね!

ある意味では、本来の能力や逸話以上に「画題」として愛されたちょっと不思議な仙人という評価が与えられるのかもしれないね。

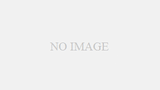
コメント