[random_button label=”他の「ハナシ」を探す” size=”l” color=”indigo”]
旅行鞄
ある夫婦。電車の網棚に旅行かばんを忘れてしまった。
どうしようかと喧嘩をするが「喧嘩をしても戻っては来ない」と、駅員に聞く事となった。
駅員は二人を事務室に連れて行き、
「どちらにお忘れになりましたか」
「そんなもの知らないよ」
「困りましたねえ。どちらの電車に乗りましたか」
「先行った山手線だ」
「山手線……今行った奴の前だから、937番ですかね。わかりました。それで何両目に乗りましたか」
「何両目なんて覚えてないよ。大塚で電車を待っていたら、ドアが開いてそれで乗った」
「何か目印とかありましたか」
「柱に上野って書いてあった」
「そんなものじゃ目標にならない。もっとパッとしたものは」
「パッとした……そういえば、十七八くらいのいい女がいて、それが僕の顔を見てニコッと笑ったね」
「そりゃお客でしょう。水飲み場があったとか、ベンチとか何かあるでしょう」
「……そういえば中央口の降り口で、その降り口と水飲み場の間だった」
「なるほど……前から四両目の二番ドアあたりですね。進行方向はどちらです」
「しんこう? シンコウは方正ですよ」
「品行方正じゃありません。行き先は右か左かですよ」
「困ったね。つり革……そのつり革がこう揺れて、ね」
「落ち着きなさい。右の方なら山の方で、丘のようなものがあったでしょう。」
「ああじゃあ右だ」
「それで品物は何です」
「ボストンバッグのピカドンの黒」
「ピカドンの黒ってのはなんですか」
「親父の形見でね、はじめはピカピカ光っていたんだが、古くなってどんよりしたから、ピカドンの黒だ」
「中には何が入っているんですか?」
「よく聞くねえ君は……」
夫婦は中に入っているものを口にするが、「やれおむすびに梅干しが入っていた」「ピンボケばかりのカメラがある」などと役に立たない話ばかり。
駅員は汗をかきながらなんとかまとめ上げ、受話器で品川駅に連絡する。
「これで連絡しましたよ」
という駅員に、妻は「これで出て来なかったら困るわ。これからうちの人のお母さんに会いに小諸へ行かなきゃいけないよ。もし出なかったら弁償してくれる?」
「冗談言っちゃいけませんよ……おや、こんな時間。私は少し食事をしますからね」
と駅員は席を立ってしまう。
残された夫婦は「なんであなたはそそっかしいのか」「お前は忘れっぽいな」と夫婦喧嘩を始める。
余りにもヒートアップする喧嘩に呆れた駅員が仲裁に入れ、「こんなところで喧嘩をなさらないでください。」
それでも二人は喧嘩を続け、挙句の果てには「新婚旅行の時は良かった」という始末。
駅員が辟易していると、そこにベルが鳴る。受話器を取ると、「荷物が見つかった」という。
「荷物が見つかりましたよ。内容も異状なし。そちらに取り行かせます」
駅員が喜んで報告すると、夫婦は喧嘩を忘れて喜び合う。
そして、旦那は駅員の対応に感謝し、「僕が国鉄総裁になったら君を駅長に推薦しよう」などとうそぶく始末。
荷物を取りに夫が出ていこうとすると妻が引止める。
「俺一人で行けばいいだろう」
という夫に、妻は首を横に振って、「だってあんた、そんなにそそっかしいんだもの。今度あたしを忘れては困るもの」
『落語名作全集5』
戦後に活躍した大野桂が、1952年の「NHK落語台本コンクール」に応募し、見事入選した作品。駅員とそそっかしい夫婦のやり取りを軽妙に描いた点が高く評価された。
このネタは二代目桂枝太郎が引き受け、枝太郎の飄逸な話術と風貌も相まって、一躍当たりネタになった。
枝太郎はこのネタをいたく気に入り、最晩年まで演じていた。
後年は、駅員を駅長にして駅長と観光客のドタバタを描いた「駅長室」というタイトルで演じていた事もあった。
枝太郎の語り口で見事に当てた、作者と演者が一体になった好例であろう。口が悪い連中は「枝太郎師匠自身が粗忽だから、そそっかしい人の描き方は地で出来る」といっていたとかいないとか。
[random_button label=”他の「ハナシ」を探す” size=”l” color=”lime”]


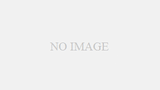

コメント