[random_button label=”他の「ハナシ」を探す” size=”l” color=”indigo”]
酒と破滅と天才肌・小金井太郎

人 物
小金井 太郎
・本 名 福井 健之助
・生没年 1891年12月24日~1936年5月26日
・出身地 千葉県
来 歴
小金井太郎は戦前活躍した浪曲師。粋でイナセな関東節を得意とし、次期「二代目玉川勝太郎」と目されながらも、酒と女で身を持ち崩し、遂に破滅的な最期を遂げた。
芝清之が『大衆芸能資料集成』の中で詳しい経歴を書いているので引しよう。
千葉県の海神で生れ、十歳のとき沢田家へ養子に行ったが、幼い頃から浪花節が好きで、暇さえあれば節を唸っているので、養父と意見が合わず。遂に勘当されて十五歳で実家に戻った。すでにその頃の彼は、街の天狗連では人気者として通っており、プロになる決心をして、十七歳で初代玉川勝太郎の門を叩いた。
芸名を玉川太郎と命名された。大正二年十月二十二歳の年に人形町の喜扇亭で看板披露をして、二十五歳で結婚した。清元、新内にも長じ、仇な小粋な節調で、太郎がもっとも初代勝太郎に似ていると言われる。俊才を謳われた太郎であったが…………、酒におぼれ、女色にふけり、為に二代目の候補でありながら後輩の次郎に継がれてしまい、やけが手伝って余計に酒におぼれ、遂には玉川を飛び出して小金井の亭号に改めた。昭和六年頃、滝の川に住んでいた正岡容に可愛がられ、名作「高橋お伝」を授けられ、SP版として残した。
養子に行った澤田家というのは太神楽の家だったらしく、養父は澤田勇次郎といった。勇次郎は神楽師に育てようとしたらしいが、稽古そっちのけで音曲に浪花節ばかり唸っているのでいつも怒っていたという。当然であろう。
初代玉川勝太郎に弟子入りし、玉川太郎。勝太郎の事実上の一番弟子であったという。その後に弟子入りしたのが、玉川次郎。後の二代目勝太郎である。
勝太郎譲りの関東節に、清元や常磐津の要素を練り込んだ物悲しく、哀愁のある耽美な節を得意とし、啖呵も見事であった。寄席の観客は太郎の耽美な節に喝采を送り、早くから「二代目勝太郎候補」と目されていた。
1913年10月、看板披露。大劇場よりも寄席読みの名人として知られ、めきめきと頭角を現した。
正岡容は玉川太郎時代からの彼を耽溺し、『雲右衛門以後』の中で、
小金井太郎
先代勝太郎門下で玉川太郎。今の勝太郎が次郎で、太郎次郎は両炎の概があった。プスッ肩先から突込んだ合口からボタボタ滴り落ちる血の紅さ。さうした果敢な節廻しであった。寂性の通りに癇癪持らしい、ぐ、ぐと念っ込んだ節の節尻には何とも餘韻の長い悲哀感が満ち溢れてゐた。「越後傳吉」の故郷踊りなどは、この人が死んで、もう誰からもあの味は地かれまい。さんざ故郷の忘じがたさを説いたのち、「それに引代へ、このごろのヤローは」と、例の「國を出るときや沢で出た が今ちや故郷の風もいや」と云ふあの唄を引いて照り「ヘッ、罰當り野郎め」と吐出すやうに云ふが否や、間髪を容れず一とふし、〽頭城郡が賀田村」と高らかに 歌ふ。「是より越後國」と誌された道路元標が、なつかしくそれに見入ってみる傳吉の旅姿が、ヌーッと大写しに目に見えて来た。
さて傳吉が故郷へかへると、しづかな日ざしに満れてあるそこかしこの藁葺から は、いろいろさまざまの人たちがゾロゾロとびだして來る。さうしてイソイソ傳吉を迎へる。その間訛りの微笑ましさ、また可笑しさ。もう、もう、こんな浪花節は聴かれない。「宇都宮釣天井」のおいねと與四郎の忍び逢いから、與四郎の死までも、太郎は得意としてみた。〽今あなたの仰せをきけば
三代様をはじめとして
列るお供の諸大名きいても
身の毛のよだつやうな
死出の旅路の釣天井……その「きいても身の毛のよだつよな」の終りの「よな」を、不思議な高音で「な アァァァ」と巧みに歌ひ伸ばしてゐてまこと身の毛のよだつを威せしめた。スケイ ルは小さいかもしれないけれど、得がたい才物であつたとおもふ。太郎は、さる美 妓との傷心事から自楽の淵に沈み、あばれ酒の限りをつくし、飲めばあやしき幻を見て狂ふ、路上つかみ合ひの喧嘩をする。さうして一生をめちゃくちゃにしてしまっ た。筆者の貧困時代にその貧乏な筆者の所へ轉げ込み同居してみたことがあったが、毎晩の観酒ホトホト困じてつひに居候の太郎をのこし夜逃げをしてしまったこともあった。それも微笑ましい思い出である。昭和十一年五月、太郎は淺草西の䧈巷で、盃を手にしたまま、ポックリ死んだ。死んだとき、棺桶の中がムンムと酒の匂ひで立ちこめた。この葬儀一切を弟弟子である今日の勝太郎が一切、花々しく営んでやった。
と絶唱している。後年、正岡容は小金井太郎に滅茶苦茶な目に合わされるのだが。
一方、早くから頭角を現し人気者になった事に加え、酒好きであった事も仇となって、凄まじい放蕩と酒乱を繰り返すようになった。
酒癖は悪く、怒りだすと出刃包丁を振り回すようなものだった、というのだから恐ろしい限りである。
正岡容は『わが寄席青春録』の中で小金井太郎に散々な目に合わされたことを記している。
再び滝野川の陋宅をも失踪しなければならなくなったのは、その頃交りを結んだ小金井太郎一家が転げ込んで来て、毎晩酒乱で太郎が凶刃を揮うため、私は神経衰弱になってものが書けなくなってしまった上に、博文館関係の雑誌が不況で二、三急に潰れ、まったく収入がなくなってしまったからである。居候の太郎一家を残して、こちらがドロンをしてしまったのだった。
また、正岡容の兄貴分であった詩人の金子光晴が自伝『詩人』の中でこんな事を書いていたりする。
ぽつぽつ、僕が日本へかえってきたことが旧人のあいだに知れてきた。
よろこんでくれたのは、往路にも世話をやかせたことのある正岡だった。彼は、当時、滝の川の凹地で、 玉川太郎、改名して小金井太郎という、哀調のあるふしで独特な、浪曲師の二階に間借りしていた。隣家には、落語家の橘の百圓(後の圓太郎)が住んでいた。
彼の肝煎で、国民新聞社の講堂で、僕の帰朝記念演芸会を催してくれた。 蝶花楼馬楽等が応援をしてくれた。その正岡が、小金井太郎の酒乱に脅かされて、唇の色まで変えて、 一家の道具をかついで、竹田屋に逃げてきた。 二匹の猫までつれてきた。
正岡が高円寺の新居におちついた頃、ふるい友人の神戸雄一が現れた。神戸の詩集の跋文を書いたこともあり、浅からぬ因縁が、ふたたび花を咲かせたというわけだ。
ちなみにドロンを知った太郎は、激昂し、正岡容の新居を探り当てて出刃包丁を振り回したという。
1922年3月、娘の美代子誕生。この子は後に曲師となった。
1926年6月、師匠の勝太郎が死去。玉川太郎・次郎の間に「二代目勝太郎襲名戦争」というべき激しい後継者戦が行われた。
芸の実力や人気だけでいけば太郎の方が上であったが、余りにも度を越えた酒と遊び、不義理が痛手となった。喧嘩が好きで怒ると往来でひとを殴り、出刃包丁を振り回すような太郎である。
結局、勝太郎襲名の世論は、実直で勉強熱心、放送やレコードの実績もあり、真面目な次郎の方に流れてしまった。
こうした徹底的な芸人気質の性格にも、小金井太郎の悲哀があったといえよう。
特に玉川次郎の襲名を推し進めたのは、ライバルの林伯猿であった。伯猿は、テキ屋の山田春と兄弟分で親分衆とも仲が良かった。自分が可愛がっている次郎に出世してもらうべく、山春に相談し、根回しをした。
山春に恩義のある幹部たちは、結局伯猿の策略の前には敵わず、また次郎が生真面目なこともあってか、鶴の一声で決まってしまったという。そう考えると、太郎は良きアドバイザー二恵まれない点も悲劇であったといえよう。
1930年6月21日、JOAKに出演し、『宇都宮釣天井』を放送。
1931年10月、弟弟子の玉川次郎が「二代目勝太郎」を襲名。深川桜館で華々しく披露を行っている。
襲名戦争に負けた太郎は、玉川一門に愛想をつかし、「玉川太郎」の名前を一門に返上。仲の良かったテキ屋の小金井小次郎一家から盃を貰い、「小金井太郎」と改名している。
小金井一家から兄弟の盃を貰ったのは、テキ屋として対立する山春への意趣返しもあったのではないか。
1933年6月16日、JOAKより全国中継で『赤尾の林蔵』を放送。
この頃、左翼浪曲なる演目を夢見た小林孝一という学生が弟子入りしている。ただ、余りの小金井太郎の酒癖の悪さにドロンをしてしまった。『政経新潮』(1974年5月号)にこんな記事が出ている。
「一つやってみろ」 座りして、肚に力を入れて声を張りあげまづい節をうなった。
「俺より声はあるな。やってみるか」
「おたのみします」
「じゃあ二年間第子入りの証文を書きな」
「それは、どういうことなんだ」
横から笑いながら正岡さんがいった。
「浪花節の弟子入りするときは、書くもんだよ」
「それにしても、二年というのは、どういうんですか」 すると太郎は
「年期は三年が巡り相場なんだが、一年まけて二年でいいや」というのである。
私はいわれるままに用心されていたらしい半紙に筆で書き、名前の下に母印をおした。
太郎はこの駄文をぬ早くふところにねじこむと、コップに酒をなみなみとつざ、ニッコリ笑ってさし出した。
「おい一杯いこう。文を撮ったからには もうおめえは俺のものだ」
やくざ上りの酒屋のおやじのような伝法口調であった。
「だがな、もしからづらかって、外の弟子にでもなってみろ、ただじゃおかねえぜ。正岡、礼をいうぜ。大学生の子を持った浪花節がいたら、べらぼうめ、お目にかかりてえや」
太郎は上気嫌になり、正岡さんとペロペロ になった。
ちょうど正岡さんの家の隣に、六畳一間の台所つきの部屋が空いていたので、翌日私は引越してきた。
その隣りに正岡さんの弟子の橘の百円のちの円太郎が住んでいた。
太郎の家は、玉ノ井の銘酒屋の並ぶ路地の外れにあった。
私は学校に行かないで、毎日太郎の家に通った。
太郎は朝から冷酒をチビリチビリ飲みながら、ケイコをつけた。滅多に笑顔をみせなかった。十三になるひとり娘の美代子が、三味線をひかされた。遊び盛りなので、私の顔を見ると嫌な顔をした。けれど太郎にしかられながら、しぶしぶ三味をひいた。
毎日、半日がかりで、発声とタンカのメリ ハリをきびしくたたき込まれた。十日通って「加賀騒動」の幕開二席をつけてくれた。
その頃、酒びたりの太郎の芸は荒れ、前座 もつかず、どん底の暮しだった。二席上げると、太郎はよれよれの木綿の紋付を出して 「明日から前座に出ろ。皆の前でやらないと、いつまでたってもうまくなれねえ。前座は紋付は着れねえのがきまりだが、おめえは格別だ。名前は勇にしな。いずれ小金井の親分に引き会わしてやるよ」といった。
私がはじめて小金井勇の名で、前座をつと めたのは、南千住のさびれたであった。入りは三十人余りだったろうか、夢中で十五分なんとかつないだ。
その夜、九時過ぎハネて帰り途に、太郎は 私をつれて飲みに入った。 「さくら二丁」
太郎は大きな声で英し郎なじみの店らしく、コップ酒とが出た。
「さあ、今夜はおめえの前祝いだ」といい出したらきかない人なので、あきらめて私はコップをうけた。 牛肉だと思って箸をつけた。
「おい、うめえだろう、これは馬肉だよ」
「えっ、馬肉、食べられるんですか」
「おめえ、食ったじゃねえか、お坊ちゃん で馬肉など行ったことがねえんだろう。これ を江戸じゃあ、さくらっていうんだ、ざまあ見やがれ」
声を出して笑った。このぶんだと、今夜も荒れるなと、私は腹をきめた、ところがコップ三杯重ねると、外にしんみりとした口で
「早くうまくなってくれよなあ、つらいこともあるだろうが、俺もそろそろ声も出なくなるし、落ち目だからな。頼りにしているぜ 美代子を相三味にしな。女房にしたっていい んだぜ。美代子と三人で来年ハワイ巡業に出かけるか。おめえ大学生だから英語が話せるだろう」
大学生は、みな英語が話せると思っているのだ。いくらでもない、その夜の寄席の上りを太郎はみなはたいてしまったに違いない。
その後、二、三の寄席の前座をつとめたがその時のことは、今でもときどき思い出す。
それからある夜、太郎は家賃を払えなくて玉ノ井の借家を追い立てられ、神さんと美代子を連れて、正岡さんの借家に転り込んできた。ふたりは毎日、朝から冷酒を飲んで荒れた。
無頼な名人気質のご両人の酒乱の相手には私もほとほと手をやいた。けれどひる間はまだよかった。隣りなので、夜中に美代子が目をこすりながら起こしにくる。毎度のことなので、しぶしぶ出かけてみると、半狂乱になった太郎が、やってみろというのだ。
「だって師に、夜中ですぜ」
「かまうこたねえ、花郎の家でうなるの が何がいいんだい」
高座そのまま真剣にはじめないとキセルで 頭をなぐられるのである。
さすがの正岡さんも、ひる、よるを問わない師の酔態にあきれ、僕に母をとられ た形で、金子光晴さんの下宿に逃げ出した。
私は太郎の悪酒は、さほど気にならなかった。けれど私を寄席に出してしのだしにしようとしている太郎が樹になった。 それに私がかい間みた浪曲の世界は人間的私生活なぞ、踏み破らなければ生きられない深い業の根があるように思われた。とても私には耐えられないと気付いたのである。
そしてまた、一人前の浪曲師になるには十年の修業を重ねなければならず、まして浪曲の創造が、どんなにむつかしいことかを 思い知ったのだった。
正岡さんが、夜逃げしてから二、三日たった真夜中、私もこっそり太郎には無断で、その六畳の部屋から逃げ出したのである。
私にかけた夢を、むざんに破られた太郎の嘆きを思えば、まことに暗然たるものがあった。今から四十一年前、昭和八年の初秋から晩秋にかけてのことであった。
因みにドロンをした小林青年は実業界に入り、戦後は『政経新潮』という雑誌会社の社長をしていたという。
1934年5月7日、JOAKより全国中継で『浅香三四郎』を放送。
1936年3月5日、JOAKより全国中継で『越後伝吉』を放送。これが事実上最後の公に出る舞台となった。
それから三カ月もたたずに死去。酒浸りの末の死であった。アル中だった事もあってか、亡骸は酒の匂いがしたそうで、初夏になっているにもかかわらず、腐敗をする様子を見せなかったという。
葬儀一切は弟弟子の勝太郎があげた。
娘の美代子は『浪曲ファン106号』のインタビューの中で、「子煩悩な父で、曲師になりたいといった際には自ら膝を叩いてリズムを教えてくれた」「借金は一切残さずに亡くなった」と語っている。春団治、志ん生などと同様にその破天荒ぶりから付いた尾ひれもある事だろう。
[random_button label=”他の「ハナシ」を探す” size=”l” color=”indigo”]

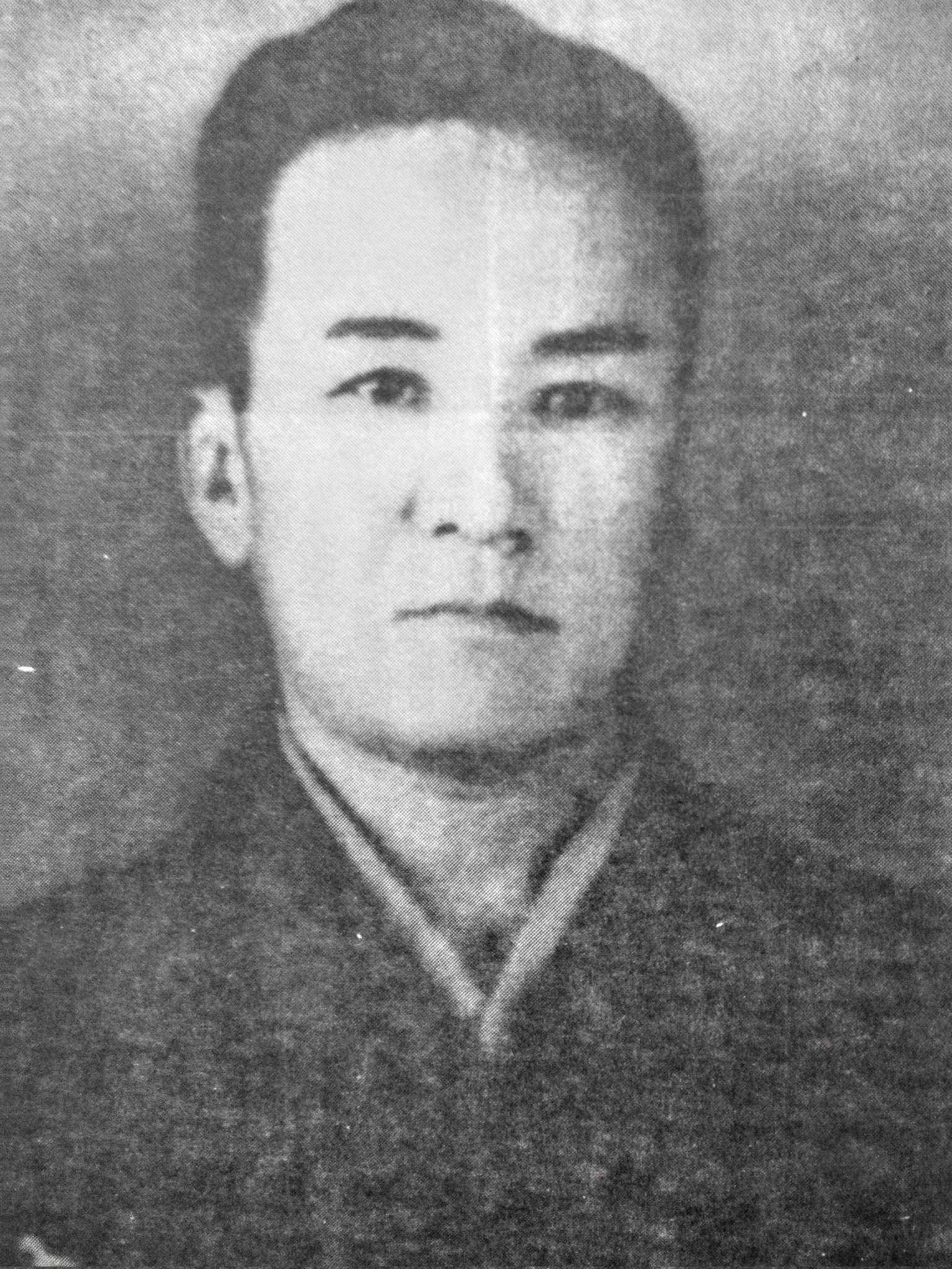


コメント