逍遥とは「ぶらつく事」?―1人目・坪内逍遥―

まずは一番目に浮かび上がってきた坪内逍遥の事を話す事に――
坪内逍遥ってどんな人?

そもそも坪内逍遥ってどんな人なんですか?

言の葉たちから見聞した話では演劇で大きな影響を与えたとか、下界にあったという早稲田大学なる名門の学校の発展に尽くしたとか……

ほう、それだけ知ってればまずまずじゃないか。確かに小説家、というよりかは、演劇研究家や翻訳家として評価が与えられがちだ。忌憚なくいえば、小説家としてはそこまでいいものを残さなかったからだね。

小説が下手だったんですか?

うーん……下手ではないが、理論ばかりというか、頭でっかちというか。まあ、わかりやすく言うと「理想論を説いて小説の進化や発展を論じたがその当事者はうまく書けなかった」というべきかな。

「うまく書けなかった?」

そう。彼の処女作的な評論『小説神髄』では、
「これまでの日本の小説は良くない点がある。これからは西洋の理念や視線を入れるべきだ」
とか、西洋的な写実や作品構造、ストーリーという概念を紹介して、後進の作家たちに大きな影響を与えた。これは大きな収穫だったといえるだろう。この一作で逍遥は近代文学の先駆けを作ったわけだ。でも――

でも?

でも、『小説神髄』と共に発表した小説『当世書生気質』は、江戸時代の戯作や滑稽本と呼ばれる伝統的なスタイルとほとんど変わりがなかった。

内容こそ明治維新や西洋の概念、料理なんか出てくるが、実態は江戸の戯作のテンプレート的な流れであった「遊び好きの青年が悪い遊びを覚えて身を持ち崩す」ってのを、明治時代に置き換えたようなたちだったわけで……そういう不完全さも小説家として大成させなかった、ともいえるかな。
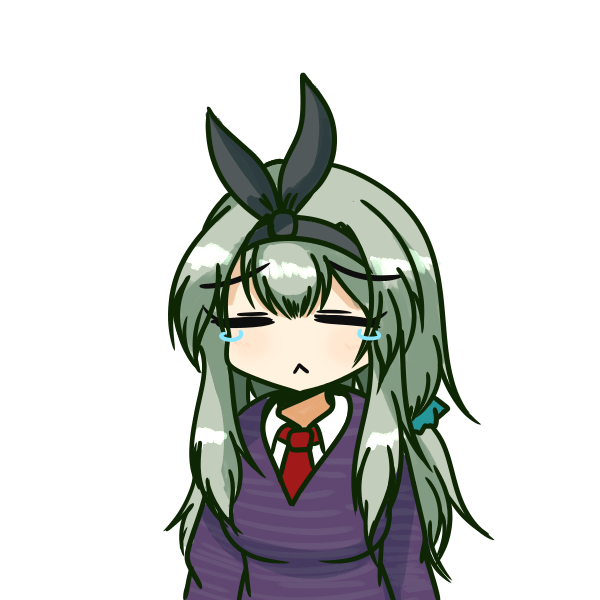
作戦だけは完璧でそれを実行できなかった、的な……

きつく言えばそうなるかもしれない。逍遥の気質や考えは、実践的な小説家よりも、多くの人を導く研究家や先生として向いていたのかもしれない。実際、その方面ではかなり成功をしたからね。

それに、逍遥の挑戦は曲がりなりにも近代文学の大きな下地になったわけだし、彼の解いた理論や小説論は他の作家たちに大きな影響を与えたわけでーー

そういう意味で、近代文学の開祖的な存在と扱われるわけですか?

そうだね。「小説」という概念を表し、日本の文芸にはなかった視点や思想を紹介しただけでも立派な開拓者。
坪内逍遥の由来

さて、本題に入るが「坪内逍遥」という名前は、本名ではない。ペンネームなんだね。本名は「坪内雄蔵」。

この「逍遥」って言葉にも一応意味があるんだけど、なんだと思う?

なんでしょう……?

「ブラブラすること」を「逍遥」っていうんだよ。

ブラブラ……?

先生、池のまわりを歩くのも逍遥に入るんですか?

それを入れるかどうかはシャーリィ君の自由だろうけど……

とにかくぶらぶら歩きさ。目的を定めず歩くこと。
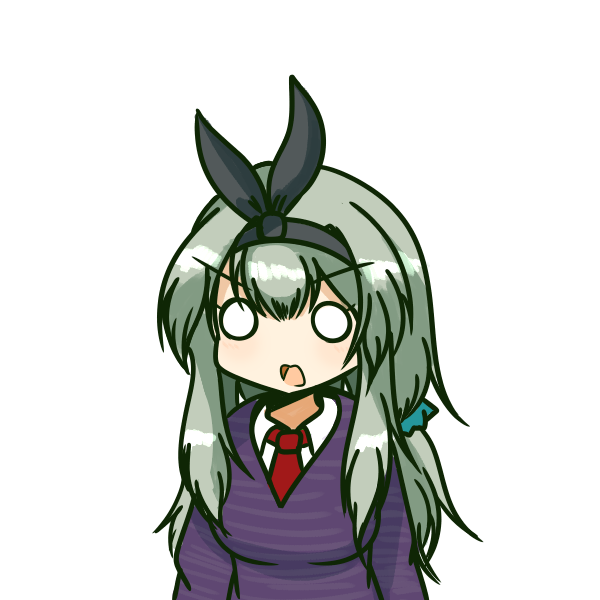
でも、どうして「ぶらぶら歩き」をペンネームにしたんですか?

通説によると、学生時代に外国語の辞典を漁っていたら「Rambler」という字を気に入った。その和訳が「逍遥」。それに、子供の頃から読んでいたという中国の古典『荘子』という本の中に、「逍遥遊」という一節があって、これを合わせた。

それで、「逍遥遊」に「人」という字をつけて「逍遥遊人」。

名前の中には「自嘲につかずブラブラしている」という自嘲の意味もあったというが……後年、「逍遥遊人」の「遊人」を切って、本名の「坪内」をつけて「坪内逍遥」が通り名になった。
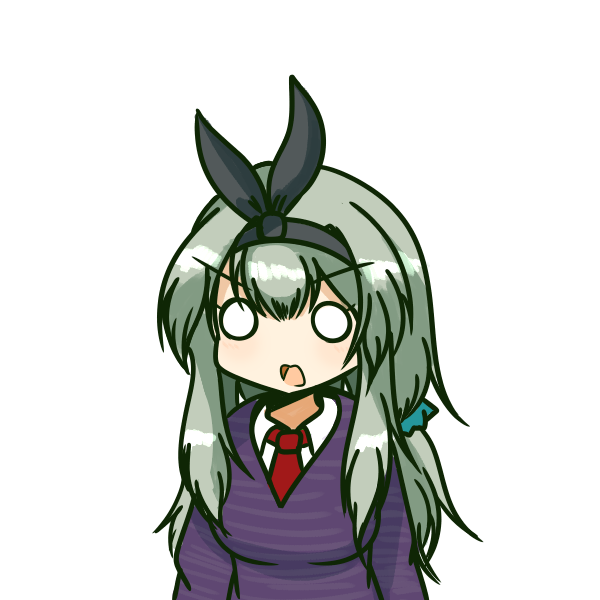
逍遥だけでもずいぶん名前を持っているんですね……?

他にもある。有名なのは「春の家おぼろ」、「小羊」とかね。

でもどうして、そんな名前をたくさんに……。

これは坪内逍遥だけの話じゃないが……昔の文学者ってのは社会的な地位が低いし、何か下手に書くと弾圧されるから隠れ蓑が必要だったわけで、ね。

もっとも、趣味人的な一面とかでわざとそう名乗る人もいる事にはいたから、全て、とも言い切れないが……。

なるほど……!!

それで「春の家おぼろ」というのは? これは、『新古今和歌集』という和歌集に収められた歌が元になっているそうだ。

『新古今和歌集』って、ずっと前に作られた和歌集ですよね。

そ。いわゆる、時の天皇が命じて作らせる「勅撰和歌集」の一つでね。勅撰和歌集の中でも重要視されてきた。 その中に、大江千里という貴族の歌が採録されているんだが、それが――
「照もせず曇りもはてぬ春の夜の朧月夜にしくものぞなき」

という。これを詰めて「春の家おぼろ」さ。

洒落ですか?

洒落だよね。こうした裏表の使い分けも、「新しい小説をうたいながら、ふざけた筆名ばかり考えていた戯作者と同じ」なんて攻撃される因縁になったわけだが……。逍遥からすれば、自嘲でもしなければやっていけなかったのかもしれない。

なるほど……それで「小羊」というのは?

これは簡単で「逍遥」という字を当てたわけさ。それに坪内逍遥が「ひつじ年」生まれだったわけで……それで「小羊」。

十二支をそのままつけたんですか……。

まあこういう事例はよくあるさ。今回のそれをまとめると――
チュン太先生はメモを取り出して、要点を書き留めた。
1、坪内逍遥は「ブラブラしている」の「逍遥」から名付けたというのが通説になっている。
2、春の家おぼろは和歌から名付けた。
3、折角の理論や考えを持ちながら、戯作的な態度から脱しきれなかったところに坪内逍遥の作家としての不完全燃焼があった。

シャーリィくん、これでお分かりかな?

……よくわかりました。ありがとうございます。
納得がいったシャーリィがお礼を言った瞬間、件の本は再び輝き始めた。

せ、先生! チュン太先生、本が輝いて……?!
そして、また「バフン」と煙を立てたかと思うと、空白だった頁に文字が浮かび上がった。

……! 先生、ページや記載が増えてますよ。
二人がページをめくると、そこには先程まで話していた「坪内逍遥」の由来が丁寧に記載されていた。
そして、「二葉亭四迷、尾崎紅葉、幸田露伴……」と、作家の名前が増えていたのであった。

……不思議な本だね。

先生の予想通り、私が納得したらちゃんと記載されて……

シャーリィ君。君はすごいものを拾ったかもしれない。こんな本は今まで見たことないよ。

本当ですか……?!言の葉たちの神様が私を導くために授かってくれたのでしょうか……?

言の葉たちの神様が私を導くために授かってくれたのでしょうか……!

いや、おおかた、君のことだから「怠けず勉強しろよ」と叱咤激励のために授けたんじゃないの?
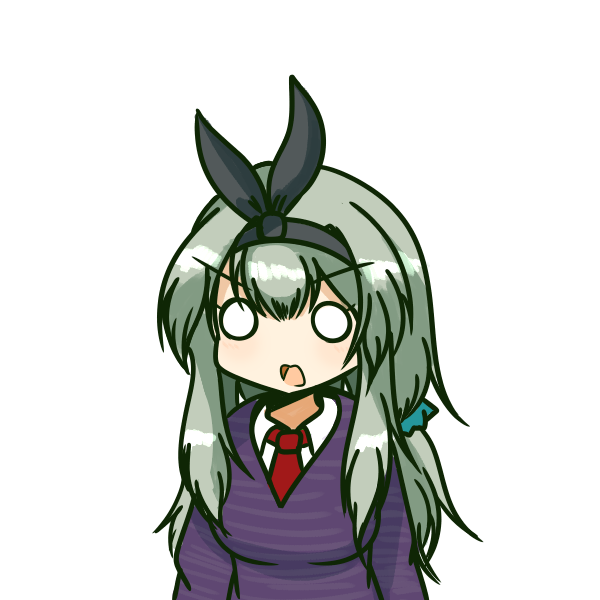
センセイ💢💢
うだうだふらふら、散っては空を飛ぶ言の葉のごとく。
二人のペンネーム千夜一夜談義は、かくして幕を開く事となったのである――

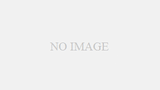
コメント