[random_button label=”他の「ハナシ」を探す” size=”l” color=”indigo”]
近眼・田山花袋とマッチのお菓子
明治39年、未だ電灯もガス灯も盛んではない頃のお話である。
国木田独歩経営の「独歩社」に、田山花袋や国木田独歩などが集まって談笑をしていた。
前田晃『明治大正の文学人』
机の上には、お茶うけのようかんや菓子が盛られた皿が出ていた。
しばらくすると、花袋は「ちょっと銀座を一回りしてこよう」と外が暗くなる前に、何人かを引き連れて、ふらりと出て行ってしまった。
各位を見送った国木田独歩、すでに平らげてある菓子皿を見つめると、何を思ったか、その中にマッチ箱を入れ、釣りランプを細く暗くした。
そして、会社に残った友人たちに向かって、
「田山が帰ってきたら、ガチリとやるから見ていてたまえ」
と笑った。
一時間ほどして、花袋たちが社に戻ってきた。各々の席に座り、また談笑をはじめた。
すると、花袋は菓子皿のマッチ箱を指でつまみ、ガチリと噛んだ。
「それやった」
と、独歩は大笑いでランプの灯を強くした。
皆が、花袋を見つめると、花袋は目を白黒させて、口を拭っていた。
一同が爆笑したのは言うまでもない。
田山花袋は『布団』『田舎教師』などで、自然主義文学を開拓した明治大正の文豪である。とやかく賛否両論される作風の持主であったが「身の回りのことを書く」だけで「小説」が成立する事を証明したことは、明治文学史上指折りの発見であろう。
小説では女性や貧困に苦しむ男や老人などを取り上げた花袋であったが、私生活では巨体で大食漢という如何にも「パワフル」という感じの人物であったというのだからおかしい。
批判や人気の低迷をかこつながらも、最後まで作家として全うし、活動し続けたのもこのような強さがあったからではないだろうか。
そんな花袋の大食ぶりは有名で、50過ぎても飯を3杯も4杯も平らげ、孫たちから「おじいさんはよく食べる」と目を丸くされた程であった。食欲旺盛のくせ、近眼であったために食べ間違いや失敗もあった。
そんな花袋の人となりを思わせる逸話であろう。
[random_button label=”他の「ハナシ」を探す” size=”l” color=”lime”]


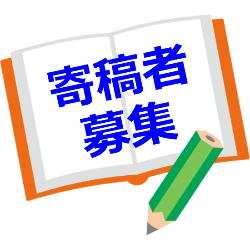
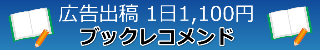
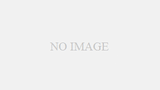
コメント