[random_button label=”他の「ハナシ」を探す” size=”l” color=”indigo”]
立ち聞きの多い腕の喜三郎
市村座の腕喜三の内で三津五郎の源太が立聞き、粂三郎の女房お磯が立聞き、友右衛門の甚三が立聞き、これぢや内所話が出来ないといふと友右衛門が、そこが芝居の浅間しさだ
1921年1月14日号
腕の喜三郎は江戸時代に実在した侠客の一人で、喧嘩で腕を大怪我したが、「こんな見苦しい腕はあってもしようがねえ」と門弟にのこぎりで落とさせ、片腕になった――という猛者で、この伝説が江戸中に知られて評判になったという。今も両国回向院にその墓がある。
この伝説をもとに河竹黙阿弥が「腕の喜三郎」という芝居を作り、市川小團次に演じさせた。粋でいなせな世話物で、江戸の観衆たちは熱狂したという。
ここに出てくる源太とは喜三郎の弟分である曙源太、お磯は喜三郎の妻、甚三は喜三郎の子分。三人とも門口に立って、喧嘩に行こうとする喜三郎の話を聞き、それで芝居をする――という筋立てになっている。
しかし、いくら芝居とはいえ、立ち聞きしている三人の姿は異様な者であろう。こう思われても仕方ない所であるよ。
ここでオチ担当になっているのは六代目大谷友右衛門。人間国宝だった四代目雀右衛門の父、今の友右衛門・雀右衛門の祖父にあたる。
憎々しい敵役が得意だったが、人間は滅茶苦茶な善人で数少ない良識人、そのギャップを含めても面白い。
[random_button label=”他の「ハナシ」を探す” size=”l” color=”lime”]


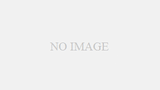
コメント