[random_button label=”他の「ハナシ」を探す” size=”l” color=”indigo”]
饗庭篁村流軍学と徳利の行方
一八九一年二月某日、饗庭篁村は幸田露伴と飲んでいた。
『徳利の行方』
いい気持ちになった二人、夜分にもかかわらず、一升徳利を掲げて友人の宮崎三昧の家を訪ねたが返事がない。
篁村は、
「玄関に置いておけば明日取り入れてくれるだろう。もう帰ろう」
というと、露伴は呆れて、
「そんなことしたら通行人の寝酒になる」
と反論し、
「門を飛び越えて入ったほうがいい」。
饗庭篁村はそれをとどめ、
「徳利に酒を入れて門外に出して置くようなものが世の中にいるだろうか。どうせ通りすがりの者にはまじないか何かにしか見えない」
と、そのまま徳利を門に置いてスタスタ行ってしまった。
ちなみにその後は森田思軒の家に押しかけ、ベロベロになるまで酒を飲んだという。
次の日、酒屋が徳利を回収しに来たので三昧の家を教えると、酒屋は怪訝な顔をして、
「先方は知らぬ存ぜぬとのこと。ない以上は徳利代を払ってください」
と、徳利代を請求してきた。
これを聞いた露伴、「それみたことか」と無謀な知恵を「饗庭流の軍学」と煽るようになったという。
饗庭篁村は、文壇の中でも相当な最年長者であったが(1855年生れ)、気風がよく、人付き合いもよかったために、多くの文士や評論家が慕ってくれた。
人当たりのいい性格だったこともあってか、関係者も「年長者」と縮こまる事なく、まるで兄弟や親類のように気心の知れた関係が構築できたという。
「根岸派」と呼ばれるグループを形成し、岡倉天心、幸田露伴、須藤南翠、森田思軒といった今なお残る文豪たちをまとめあげたのも、そういった人柄ゆえであろう。
年長者で、実力もあったが、何処かとぼけていて、関係者は「まただよ」とあきれながらも、仲良く付き合っていたという。
そんな饗庭篁村のおとぼけぶりをみせた逸話といえるだろう。
[random_button label=”他の「ハナシ」を探す” size=”l” color=”lime”]


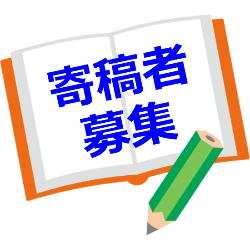
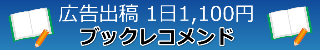
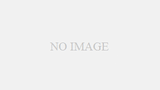
コメント