[random_button label=”他の「ハナシ」を探す” size=”l” color=”indigo”]
『吾輩は猫である』の結末を聞かれた夏目漱石
1906年5月30日、神田某所で帝大英文科所属の学生たちの宴会が行われた。同大の教授、夏目漱石も列席し、夜通しどんちゃん騒ぎ。
ある学生が酔った勢いで漱石に向かって、
「先生、今書かれている吾輩は猫である、の始末はどうおつけになりますか」
酔った漱石も漱石で、澄ましきった態度で、
「うむ、めんどくさいから、次回あたりで殺してしまう考えだ!」この2か月後、主人公の猫は水がめの中でおぼれて死ぬ羽目になる。「ありがたやありがたや」
『読売』(1906年6月2日号)
夏目漱石の代表作としてまず第一に挙げられるのは『吾輩は猫である』であろう。
その明瞭なタイトルもさることながら、独特なユーモアを携えたそれは、近代小説に大きな影響を与えたほか、パロディや漫画のタイトルの大きなドル箱となった。
『吾輩は猫である』が俳句雑誌『ホトトギス』に掲載されたのは、1905年1月から1906年8月まで。漱石は、『ホトトギス』の代表で友人であった高浜虚子に勧められて気楽な気分で書き始めたのがそもそものキッカケである。
漱石もそこまで肩ひじ張らずに好きな作品や落語のパロディや引用で書いていたが、そのこんこんとわき出でるユーモアや「猫」という非人間の視線という新しい書き方がたちまち注目され、自然主義や深刻小説でやたらと陰湿極めていた小説界に、新風を招いた。
回を重ねるごとに『吾輩は猫である』の評判は高くなり、『ホトトギス』の売れ行きも評判も好調になった。高浜虚子からすれば、漱石大明神と拝め奉りたくなるほどの売れ行きだったに違いない。
そんな『吾輩は猫である』も、結末が近づくにつれ、「最後はどうまとめるのか」という読者や関係者の声がささやかれるようになった。
その中で平然とすっぱ抜かれたのが上の記事である。しかし、これはあくまでもゴシップだったようで、記事の中に「宴会の最中、泥酔の最中」と前置きがある所からあくまでも「酔客のタワゴト」程度の扱いだった模様。
読者や新聞記者も「酔っぱらって馬鹿な事言ってんな」程度に感じていたのだろう。
しかし、その「猫を殺してしまおう」という漱石の放言は、的中する事になる。既にこの頃には結末の構想が練られていたのであろう。
皮肉にも「ゴシップ」として出したそれは、漱石の構想を証明する貴重な証言となったわけである。
[random_button label=”他の「ハナシ」を探す” size=”l” color=”lime”]


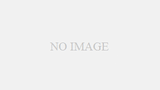
コメント